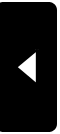2011年02月25日
まちづくりの経営リテラシー
第28回 まちづくりコラム 「問われる、まちづくりの経営力」 木下 斉 氏
https://www.machigenki.jp/content/view/357/93/ より転載
(1)事業目的を設定する際に「因果関係」を意識する。
因果関係の整理は経営力の基礎です。全ての課題には原因があり、その原因解決のためにまちづくり事業は存在しています。この因果関係認識の徹底は当然のようで実はあまり現場では出来ていません。地域の抱える課題を体系的に整理せずに、因果関係と直結しない目の前にある課題に日々取り組んでしまっていることが多くあります。当然ながら結果ができません。
例えば、イベント事業でも何の原因解決のために取り組んでいるのか、因果関係を意識しながら取り組む必要があります。例えば、売上げ減少に悩んでいるという課題解決のためのイベントであれば、通りに人集めに留まらず、実際にその顧客を各店舗に送客する仕組みまで考え実行してようやく事業の目的と合致します。しかし現実にはこの集人から集客への動線の仕組みまで踏み込まず、当日の設営や人集めなどに力を注ぎ込んでしまっていることが少なくないのです。
(2)事業には戦略が必要
まちづくり分野の成功事業分析で、戦略分析が行われたことは非常に少ないです。もしくは勘と経験とキーマンとなる人材論に終始してしまい、理論的整理は古くて不要という意見も聞きます。
しかし事業が成果を上げているのはしっかり戦略合理性が成立していることには違いありません。脈略もなく適当にやるだけで成果が出ることはなく、成果が出ている事例の背後にはしっかりとした合理性があります。例えばまちづくり事業でコミュニティカフェを経営する場合にも、利用する側は単にカフェという点では他のカフェと比較する=競合があり、それら他の競合との間に差別化できる立場を築く必要があります。戦略分析の基本的な考え方に基づいて、事業設計を進めるだけでも経験や勘を持ち寄るだけの議論とは違う結果が導き出せます。
(3)人材依存だけでなく、組織能力を形成する
まちづくり事業を推進する際には、一部のキーマンの存在などに偏った分析が多いですが、継続的に事業を進めるためには確実に組織能力を形成する、キャパシティビルディングの視点が不可欠です。 自分たちのまちづくり組織に人を入れるという考え方だけでなく、複数の団体とのアライアンスなど自分たちが活用できるリソースを可能な限り拡充していく考え方を持ち、組織的に事業へ活用していくことが有効です。
また、まちづくりにおいては安易なネットワーク組織優位の考え方などが多く、ヒエラルキーを否定する傾向もあります。しかし、決まった業務を遂行するには一定のヒエラルキーモデルの方が適していることも事実です。取り組む事業の性質によって組織のあり方も変えていくためにも組織論は役立ちます。
(4)財務的な理解が、事業をカタチにする。
財務的な視点はまちづくり組織経営上、重要であるにも関わらず、あまり取り上げられない要素でもあります。まちづくり会社の設計においても、「コストセンター(非収益部門)」と「プロフィットセンター(収益部門)」とをバランスさせなければ、当然ながら組織経営は継続できません。しかしプロフィットセンターを補助金など他組織予算編成で大きく変動を受けてしまう内容に限定してしまい、コストセンター事業ばかりを作ってしまえば経営は一気に不安定になってしまいます。現実として、そのようなまちづくり会社が多く存在しています。
また、個別事業においても同様に想いや目的は優れていても、民間事業として推進できない事業構造であることも多くあります。事業設計時点で、事業の財務構造を決定してシミュレーションを実施していないことがその原因であることに、多くの地域で直面します。
(5)プロジェクトマネジメントが、短期事業立ち上げを実現する。
まちづくり事業には「リードタイム」という概念があまりありません。リードタイムとは作業に取りかかってから、終了するまでの時間のことです。まちづくり事業の多くは調整作業に費やされ、実際の事業立ち上げまでに時間がかかることは現実としてあります。私は基本的には勝ち馬に乗らせるということを基本としているため、初期には合意形成よりは事業に賛同する少ない関係者からスタートすることを優先して、可能な限りリードタイムを短くすることに徹しています。
そしてプロジェクトを初期に設計して、作業と時間と担当者を決めて推進する管理を賛同者たちで進めます。これを徹底すると短期間に事業を立ち上げて推進することができ、無用なコンセンサス形成による関係者の機会損失が拡大することやモチベーションの低下を防ぐことができます。
https://www.machigenki.jp/content/view/357/93/ より転載
(1)事業目的を設定する際に「因果関係」を意識する。
因果関係の整理は経営力の基礎です。全ての課題には原因があり、その原因解決のためにまちづくり事業は存在しています。この因果関係認識の徹底は当然のようで実はあまり現場では出来ていません。地域の抱える課題を体系的に整理せずに、因果関係と直結しない目の前にある課題に日々取り組んでしまっていることが多くあります。当然ながら結果ができません。
例えば、イベント事業でも何の原因解決のために取り組んでいるのか、因果関係を意識しながら取り組む必要があります。例えば、売上げ減少に悩んでいるという課題解決のためのイベントであれば、通りに人集めに留まらず、実際にその顧客を各店舗に送客する仕組みまで考え実行してようやく事業の目的と合致します。しかし現実にはこの集人から集客への動線の仕組みまで踏み込まず、当日の設営や人集めなどに力を注ぎ込んでしまっていることが少なくないのです。
(2)事業には戦略が必要
まちづくり分野の成功事業分析で、戦略分析が行われたことは非常に少ないです。もしくは勘と経験とキーマンとなる人材論に終始してしまい、理論的整理は古くて不要という意見も聞きます。
しかし事業が成果を上げているのはしっかり戦略合理性が成立していることには違いありません。脈略もなく適当にやるだけで成果が出ることはなく、成果が出ている事例の背後にはしっかりとした合理性があります。例えばまちづくり事業でコミュニティカフェを経営する場合にも、利用する側は単にカフェという点では他のカフェと比較する=競合があり、それら他の競合との間に差別化できる立場を築く必要があります。戦略分析の基本的な考え方に基づいて、事業設計を進めるだけでも経験や勘を持ち寄るだけの議論とは違う結果が導き出せます。
(3)人材依存だけでなく、組織能力を形成する
まちづくり事業を推進する際には、一部のキーマンの存在などに偏った分析が多いですが、継続的に事業を進めるためには確実に組織能力を形成する、キャパシティビルディングの視点が不可欠です。 自分たちのまちづくり組織に人を入れるという考え方だけでなく、複数の団体とのアライアンスなど自分たちが活用できるリソースを可能な限り拡充していく考え方を持ち、組織的に事業へ活用していくことが有効です。
また、まちづくりにおいては安易なネットワーク組織優位の考え方などが多く、ヒエラルキーを否定する傾向もあります。しかし、決まった業務を遂行するには一定のヒエラルキーモデルの方が適していることも事実です。取り組む事業の性質によって組織のあり方も変えていくためにも組織論は役立ちます。
(4)財務的な理解が、事業をカタチにする。
財務的な視点はまちづくり組織経営上、重要であるにも関わらず、あまり取り上げられない要素でもあります。まちづくり会社の設計においても、「コストセンター(非収益部門)」と「プロフィットセンター(収益部門)」とをバランスさせなければ、当然ながら組織経営は継続できません。しかしプロフィットセンターを補助金など他組織予算編成で大きく変動を受けてしまう内容に限定してしまい、コストセンター事業ばかりを作ってしまえば経営は一気に不安定になってしまいます。現実として、そのようなまちづくり会社が多く存在しています。
また、個別事業においても同様に想いや目的は優れていても、民間事業として推進できない事業構造であることも多くあります。事業設計時点で、事業の財務構造を決定してシミュレーションを実施していないことがその原因であることに、多くの地域で直面します。
(5)プロジェクトマネジメントが、短期事業立ち上げを実現する。
まちづくり事業には「リードタイム」という概念があまりありません。リードタイムとは作業に取りかかってから、終了するまでの時間のことです。まちづくり事業の多くは調整作業に費やされ、実際の事業立ち上げまでに時間がかかることは現実としてあります。私は基本的には勝ち馬に乗らせるということを基本としているため、初期には合意形成よりは事業に賛同する少ない関係者からスタートすることを優先して、可能な限りリードタイムを短くすることに徹しています。
そしてプロジェクトを初期に設計して、作業と時間と担当者を決めて推進する管理を賛同者たちで進めます。これを徹底すると短期間に事業を立ち上げて推進することができ、無用なコンセンサス形成による関係者の機会損失が拡大することやモチベーションの低下を防ぐことができます。
Posted by cho8 at 12:55│Comments(0)
│まち