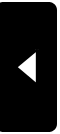2015年05月28日
チガヤ



チガヤ@R152中央分離帯
近年、中央分離帯を制圧している感じのチガヤ。在来の雑草の代表。ま 雑草とは人間の都合だし、生態系を壊しているのは人間の経済活動によるものだし。ここのところの花粉症のアレルゲンはチガヤなのかな?それともPM2.5?もしくは放射性物質・・・? チガヤはそろそろ終わりの模様。
※河川敷におけるチガヤヒメジョオン群落
http://www.skr.mlit.go.jp/yongi/syokusei/kaisetsu/chigaya_himejyon/
■構成種
群落高は1 ~1.5m 程度である。構成種にはヒメジョオン、カスマグサ、キンエノコロなどの一年・越年生やニガナ、カワラナデシコ、ヨモギ、スギナ、セイタカアワダチソウなどの多様な植物から構成される。構成種数は数種から29 種と幅がある
■成育立地の環境特性
本群落は基本的に、1 年に2 ~3 回程度の刈り取り管理を受けている堤防法面や高水敷などに成立する。刈り取り頻度と成立する植生型についてはススキ群落の頁に詳しく述べている。一方、海岸付近には刈り取りなど人為の影響を受けない自然性のチガヤの優占群落があり、ハマゴウ-チガヤ群落の1 タイプと考えられるが、詳しくは明らかとなっていない。そのような群落もこれまでの河川水辺の国勢調査で調査されているが、群落の位置づけが明らかでないこと、ごくわずかな調査資料だけなので、今回はそれらもチガヤ-ヒメジョオン群落にまとめた。
■生態的機能
多様な植物から構成され、チョウが食草とする種が多く含まれることから草原性の生態系の基盤として優れた植生である(ツマグロヒョウモンチョウ(中):食草はスミレ類(左)、ジャコウアゲハ(右):食草はウマノスズクサ)。また、チガヤの根茎は密に成育して土壌を保全する。さらに野草観察などアメニティ性も優れ、多機能を備えた優れた植生である(服部他、1994)
■保全上の留意点および保全・創出に関する事柄
前述したように堤防、高水敷など広大なスペースに成立する草原として、環境的価値は高い。現状で刈り取りなどの管理が続けられれば、本群落は維持されていくと考えられる。チガヤ群落の創出には、根茎をつけた株を移植する方法、種子をまく方法などがある(チガヤ草原創出研究会、2000)。このうち、株の移植による群落の創出は、比較的容易である。なお、近年は、チガヤの持つ環境機能に注目され、チガヤ苗や各種緑化資材が流通している。
■植物社会学上の位置づけ
チガヤ-ヒメジョオン群集、シバ群団、シバスゲオーダー、ススキクラスである。
http://bit.ly/1RsnNlQ
分布・形態
■分布
ユーラシア大陸、アフリカ大陸の暖帯に広く分布する種で、日本全土に分布する。
■形態
根:根茎は白く、地中を長く這う。
茎:4月頃発芽して成長、茎はやや細く、直立して高さ30~80㎝になる。
葉:葉は長い線形で長さ20~50㎝、幅7~12㎜、緑褐色でやや堅く、下部は狭まって葉柄のようになる。
葉鞘には通常毛があり、基部は褐色で古いものは繊維状になる。
花:花期は4~6月。葉が出る頃に穂を出す。果穂は円柱状で長さ10~20㎝、白い長毛に囲まれ、枝は短い。小穂は長さ約4㎜、両性で、総の中軸の関節に2個ずつつく。
■類似種
河原や土手で、5~6月に銀白色の穂が揺れるようなイネ科植物は他にないので、間違えることはない。
■生育場所
河原や堤防の法面、海浜、畑の畦道などに群生する。陽当たりの良い乾いた草地、特に砂質地に多い。
■繁殖
繁殖は主に地中を長く這う地下茎(根茎)によって行なわれ、その節々から先の鋭い線形の葉を出して群生する。
4~6月に花穂を出し、結実する。
果実は穎果とよばれる小型の乾果で芒はなく、果皮は膜質で薄い。熟すると基盤の白い長毛とともに総から脱落し、風で飛散する。
(2011.1.24._川口(RFC)_リバーフロント整備センター編(1996)川の生物図典)
■他の生物との関係
ヒメウラナミジャノメ、キマダラモドキ、ウスイロコノマチョウ、ギンイチモンジセセリ、イチモンジセセリ、チャバネセセリ、ユウレイセセリなど、多くの蝶類の食草となる。
セッカなどの鳥類の営巣や生息の場となるほか、昆虫類や小動物の生活の場ともなっている。
(2011.1.24._川口(RFC)_リバーフロント整備センター編(1996)川の生物図典)
■配慮のポイント
チガヤの草原には多くの昆虫や鳥が依存しているので、草刈り、火入れなどの管理を行なう際には時期や頻度に配慮して、生物の生息に影響を及ぼさないようにする。
(2011.1.24._川口(RFC)_リバーフロント整備センター編(1996)川の生物図典)
■トピックス
根は茅根とよばれ、漢方薬(利尿薬)として利用される。
最近では、堤防の法面保護のためにチガヤを用いることも検討されている。
(2011.1.24._川口(RFC)_リバーフロント整備センター編(1996)川の生物図典)