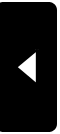2012年10月10日
「造園界の今後のあり方」
「造園修景」No.119 より 特集 「造園界の今後のあり方」
(一般社団法人)日本公園緑地協会 顧問 山田勝巳氏
1.はじめに
経済のゼロ成長時代を経由して世界は成熟期の段階に入り、文明の大きな転換期にいる。
多様な価値観、交流と連携、社会貢献、グローバリゼーションという社会意識の転換によりヒエラルキーな社会構造からフラットな社会構造に変わりつつある。タテ社会からヨコ社会へ移行していく。
人々の生きがいと価値観は、物から、人・サービスーへ、また人を感動させ、幸せにする社会、人と人との交流、連携、絆であり、社会への貢献に変化していく。
2.自然と人間の共生
公害対策で「経済と自然との調和」、花博では「人と自然の共生」、愛知博では「愛・地球博-自然の叡智-」へと変遷した。
自然と人間の関わりは経済優先から「人間のための自然」にまで深化した。
緑の社会資本は一定の水準にまで引き上げられ今後は、再生やメインテナンスに重点が置かれていく時代になっていく。大震災の復旧・復興、原発事故、デフレ経済など多難な時期に今後の造園界を見つめると先行きの見通しは難しいが、世の中の新しい動き、新しい需要に向かって、造園家が総力をあげて結集し未来を切り開いてゆく機運を作り出していくことが大切であり、時には思い切った発想の転換も必要であろう。
(1)造園の目指すものは
造園は技術の範疇にあり、技術は科学によって得られた客観的な自然的法則の人間社会の実践のための意識的適用である。
したがって「造園は生物社会を構成する生態系という自然を保護、保全、改変、創出し良好な人間環境を創り出す技術である」ということになる。
里山の人々と縁との関わり方が良好な人間環境を創り出してきた、といわれるが現状は相当厳しい。
街路樹も同様で、定期的な勢定により樹形の美しさが保たれるが、これを怠るとしばしば近隣住民とトラブルにになり管理者、住民、造園家が話し合い、解決していく事例が見られる。ホノルル市では市内の樹木や緑被地をアーバン・フォレスト(都市林)として捉え24時間体制で市が管理にあたり、最良の景観地区を保っている。
(2)造園家と造園界の今後は
造園家と造園界の役割と使命は人間に快適で感動を呼び、人を幸せにする自然と環境をいかに世の中に提供するかにある。公園緑地は人々に日常生活の中で健康、運動、福祉、観光・レクレーション、教育といった様々なサービスを提供できる施設であり、人々の生活に関わる自然や、環境には公園緑地という施設の単一機能だけでなく、広域の自然や、環境が保有する景観、生態系、地球環境、生物多様性、安全・安心な街づくりといった、総合的、複合的な役割を担っている。
各種の専門家、住民、行政、首長を交え、現況把握、構想・計画、施工、管理運営まで幅広く、説明し、賛同を得て、問題の解決、計画の実現、管理運営の手法、改善などに役立っていくことが必要で、このためのノーハウ、仕組みについて新しい技術や考え方を駆使して、新たな価値、システムを生み出し社会を、大きく変える変革を起こすことが求められているのでは。
3.社会や利用者のニーズあった公園緑地
(1)時代とともに変化するニーズ
公園緑地に対する社会のニーズは時代とともに大きく変遷していく。これに絶えず即応していかないと社会から無用のもの、無駄使いと言われかねない。次に具体の施策との関連を見ていくと
① 歴史まちづくり・緑地保全
緩やかな規制で緑地保全の効果を上げ、管理も可能になっている。管理の指定団体の充実やNPOの組織化が急がれる。
歴史まちづくりは全国の市町村が望んでいた仕組みで今後の推進が期待されるが、これはまさに造園専門家が関係者をコラボレートして進めていく題材であろう。
横浜市が緑地保全の財源として市民から一定期間の特別徴収に踏み切ったのは英断といえる。
② 街区公園
公園の遊具による事故が頻発し安全基準が業界独自でも見直し改定され、その後の事故防止に貢献している。
遊具の老朽化対策や効率的投資を目的に公園施設長寿命化計画が策定され街区公園がリフレッシュされ子供と母親の人気を集めている。全国的に進めてもらいたい施策である。
③ 防災公園
東日本大震災による津波で重要性が確認された公園緑地の機能に、多重防御の一つとしての機能がある。多重防御には樹林地による津波エネルギ<減衰機能・漂流物捕捉機能、湛水の場としての空地等による津波被害軽減機能があげられている。過去の戦災復興、震災復興の経験を活かし、思い切ったデザインを提案し、復興の目玉になっていくことを望みたい。
東京都江東区の篠崎公園(旧防空緑地)では、地盤を景観も考慮に入れて6メートル嵩上げした整備計画が策定されている。
④ 国営公園
年間利用者数200万人を超える国営公園が2か所ある。
昭和記念公園は自然再生、温暖化対策、生物多様性、防災避難地、災害救助拠点、レクリエーションなどあらゆる機能を有し、首都圏人口集中地の多様なニーズに応えられる優れた資産にまで成長した。首都圏にさらに2~3箇所ほしいところである。
沖縄記念公園首里城公園は沖縄本土復帰20年を記念して創設された。沖縄県民の魂ともいうべき存在であった首里城を戦火で全く荒廃した中から今日の姿までに復元にいたった。その間の関係者の想像を絶する気迫と気概の結集で実現できた。おそらく造園史上、文化資産の復元による数々の知識と技術の集積は日本最高のものであろう歴史的文化的資産の復元は伝統的技能や技術の再生、新たな開発に貢献し後世にまで伝承していくことになり計り知れない大きな資産となって蓄積されてくことになる。
海洋博公園地区は沖縄振興の一環で記念公園として設置され、博覧会当時の水族館が老朽化し、沖縄復帰30周年記念を目指し改築されることになった。基本コンセプトは沖縄の海域を流れる暖流の海原を一断面に切り取った姿を見せることであった。ここにジンベイザメ3匹が悠々と泳ぐ様は人々を感動させ生きがいを感じさせると言っても過言ではないかもしれない。自然に近い海の生態の創出に成功しているのではないかと思われる。
⑤ 生物多様性
生物多様性の確保に関する取り組みとして「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」を定め4つの緑地の拠点を配置するこにした。緑の基本計画の活用により具体的な事業への展開が期待されるが、計画本体とは別に住民にわかり易い参考図的なデザインにより関係者に説明する造園専門家の助言、支援ができる組織があれば住民に便利である。
⑥ 地球温暖化と都市緑化
都市の緑はCO2の吸収源として、また太陽光を遮り、樹林が葉面から蒸発散を行うことにより冷気を吹き出し、熱環境改善効果を発揮する。
都市の緑のCO2吸収効果や大気改善効果を小規模な地域で定量化して、住民にわかり易くリアルタイムで提示できれば都市の緑を保全し、拡大していくための全く新しい評価基準が確立することになる。
緑化地域制度や地区計画等緑化率条例制度の積極的な活用を目指した啓発普及、実践活動を推進させていきたい。
⑦ 新エネルギーと節電
新エネルギーの開発が急がれるが広大な敷地を要する太陽光パネル方式に替えて小規模方式、例えば発電資材として薄型で緑色の菓面状の素材が試作されているが、技術アップして、発電効率の良い資材が出来れば太陽光発電ツリーの誕生もありうる。景観対策上も大きな変革になる。
さらに、節電対策として、緑化による大気温度の低減効果と風の道を期待する街づくり、都市計画が動き出している。
⑧ 景観
景観計画の策定、景観協議会、景観整備機構の発足・運営、景観教育など造園専門家の助言、協力を積極的に進めていきたい。
また、我が国の「道」の原点である日本橋は、優れた歴史文化資産であるが、東京オリンピックの折、首都高速に上空を占用許可した。昭和41年当時最初の赴任地は日本橋を管理する東京国道で、所長が誠に残念至極と嘆いていたのを思い起こす。道路景観の取り組みだった者としてはこの機会に日本橋を上空占用から解放する一大事業に取り組んで頂きたいと願っている。
⑨ パークマネジメント
どのような管理を目指すべきか、利用者や社会のニーズは何か、いかに高品質のサービスを提供するか、と多くの期待が寄せられている指定管理者制度であるが、その後の運用に懸念が生じている。過度な市場原理主義、事業者への縛り、公益・一般法人と営利法人との適格性等、本来の趣旨に根ざした方向に改善が望まれる。
(2)地域リーダーの育成
地域主権が今後どのように進展するかまだ不透明だが確かなことは首長や役所だけでは限界があり、市民の協力がいる。地域のニーズをくみ取り人々を正しい方向に導く「リーダー」が必要で、各種の分野の専門家、住民、行政、首長を一定の目標に向かってコラボレートしまとめあげていく能力を有するリーダーを育てていく研修・教育制度を充実し、一定の資格制度にまで発展させる仕組みが求められていると思う。
4.おわりに
先の大震災で争いごとは起きていない。世界中の賞賛を受けた。地縁・血縁の共同体意識ではなく、共通の利益を尊重し、発展的に連携していく人と人との杵が新たな時代のチカラとなる。
日本人は古来より、花と自然を愛し、日本庭園にみられる優れた伝統的な独自の文化を築き上げてきた。美しいものは素直にきれいだと感動するのが「大和ごころ」と本居宣長の歌を想い起こしつつ未来に向けての新しい自然と人間の関わり方を探ってゆきたい。
Posted by cho8 at 13:00│Comments(0)
│造園